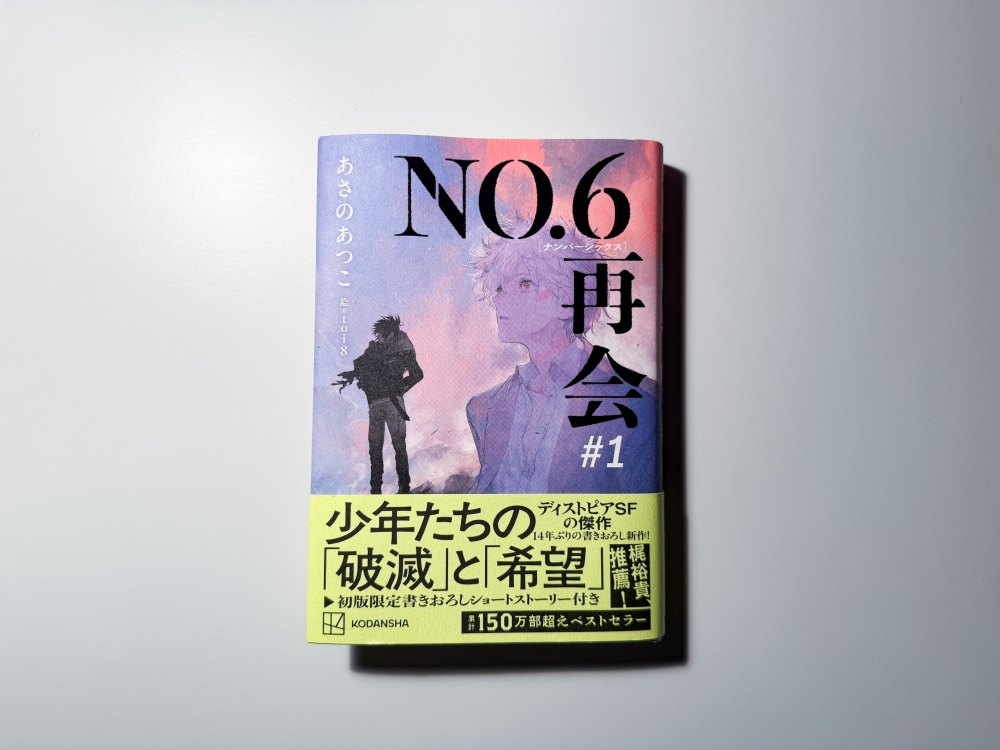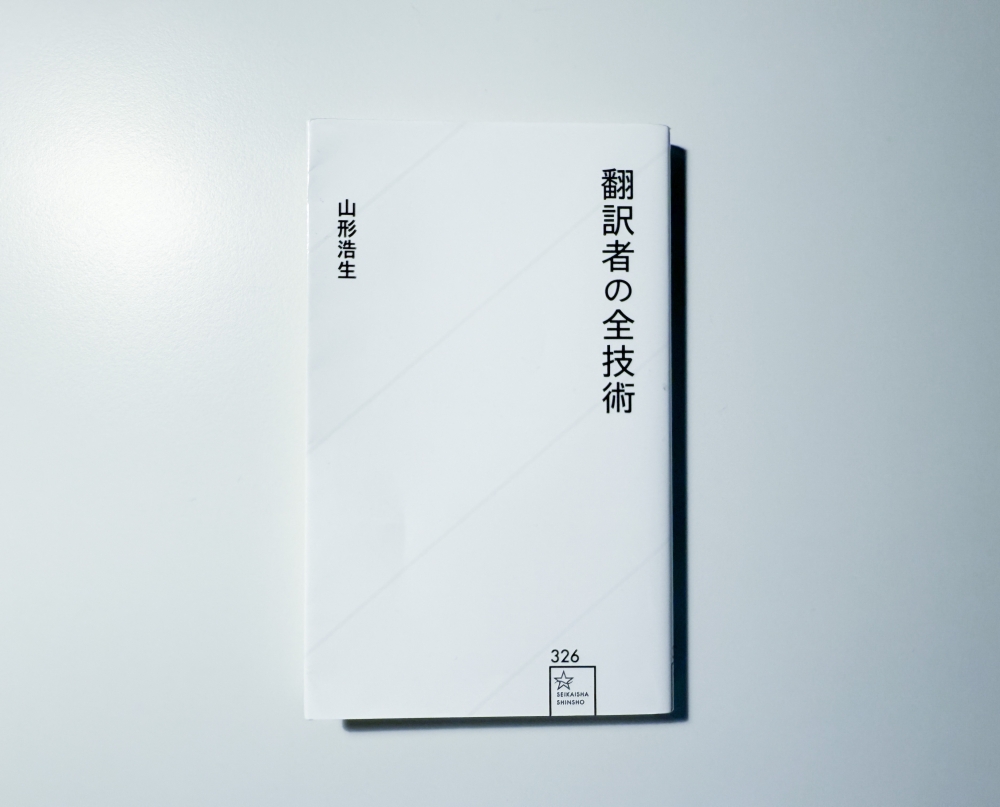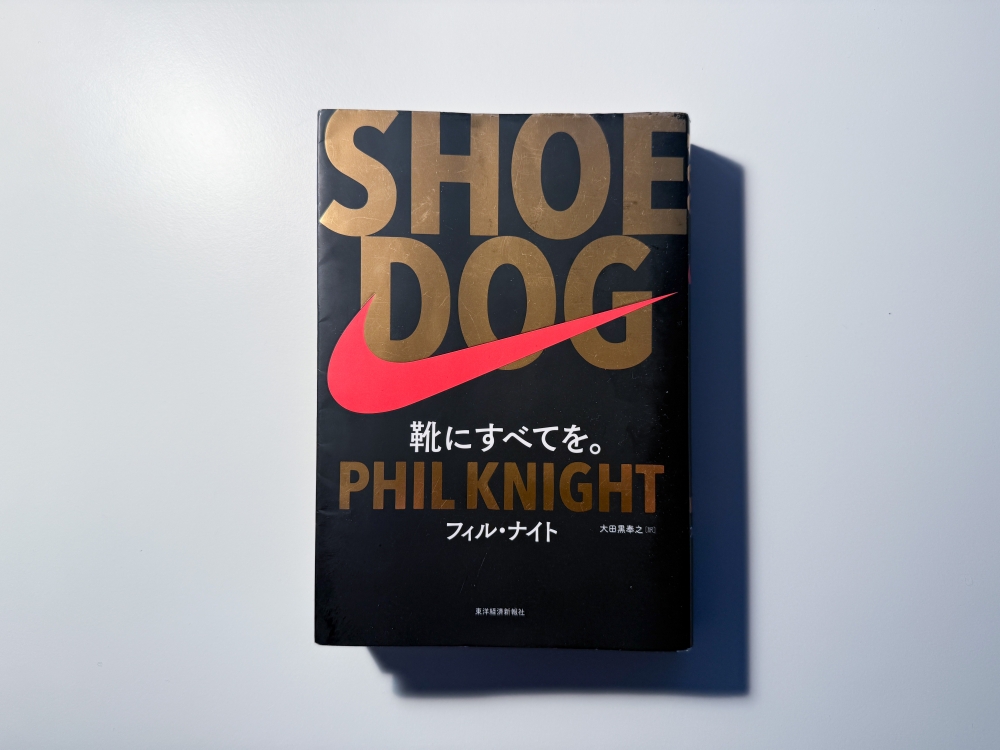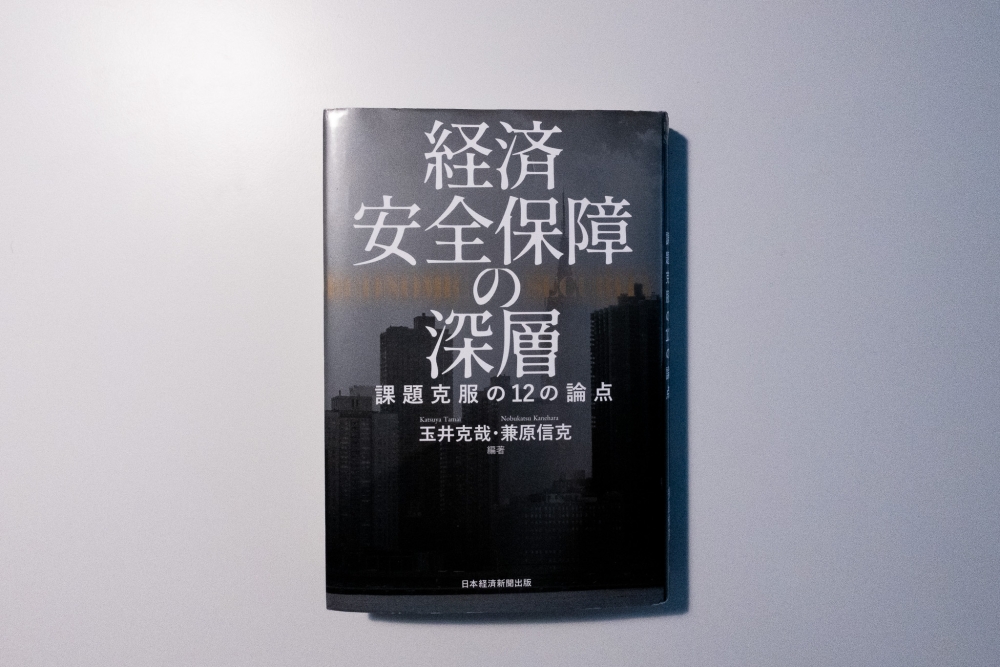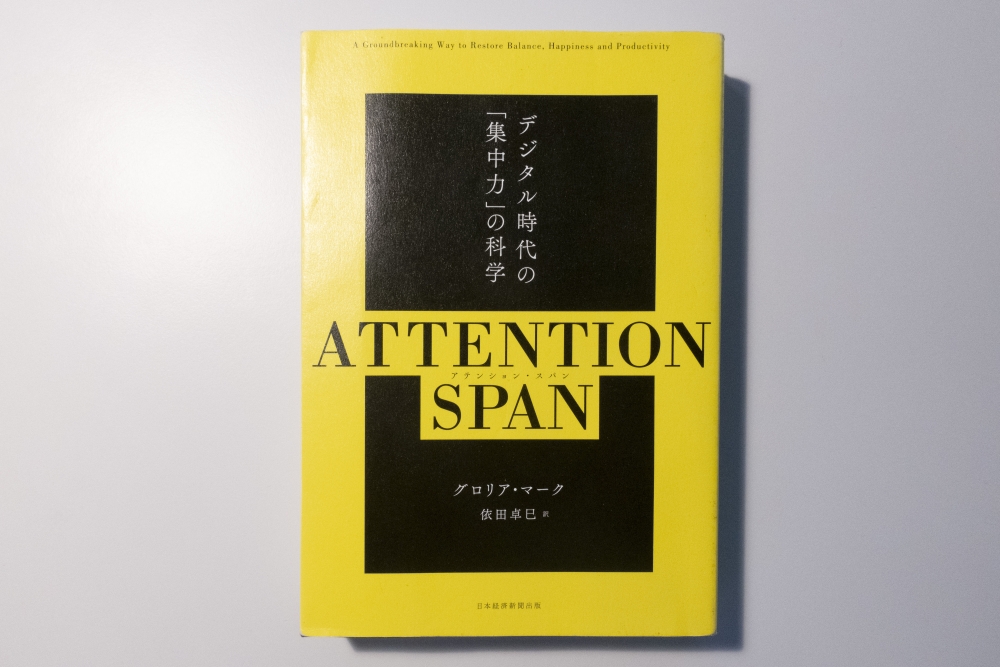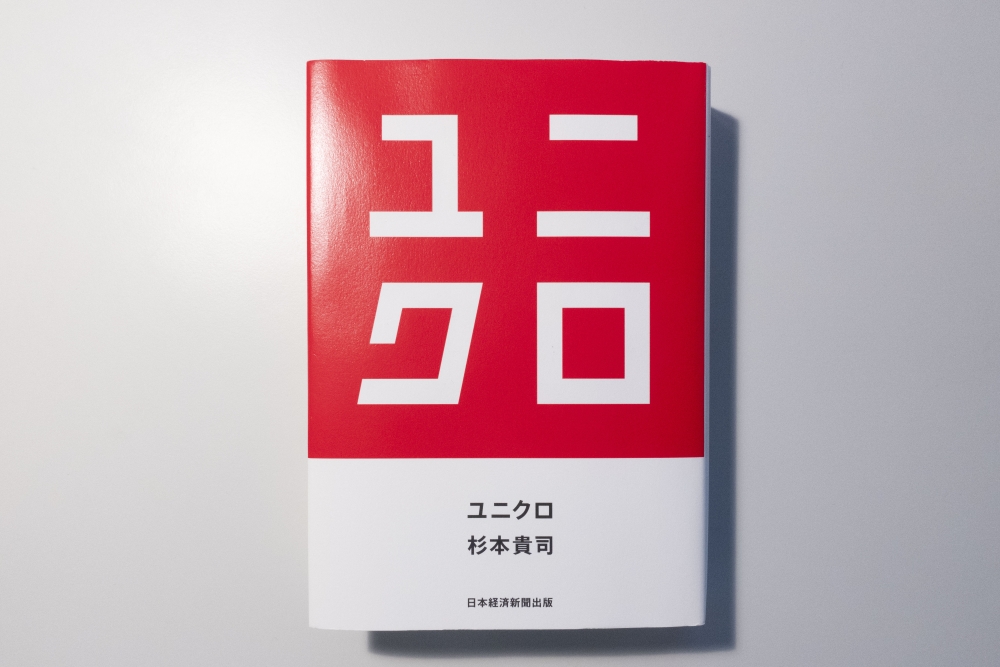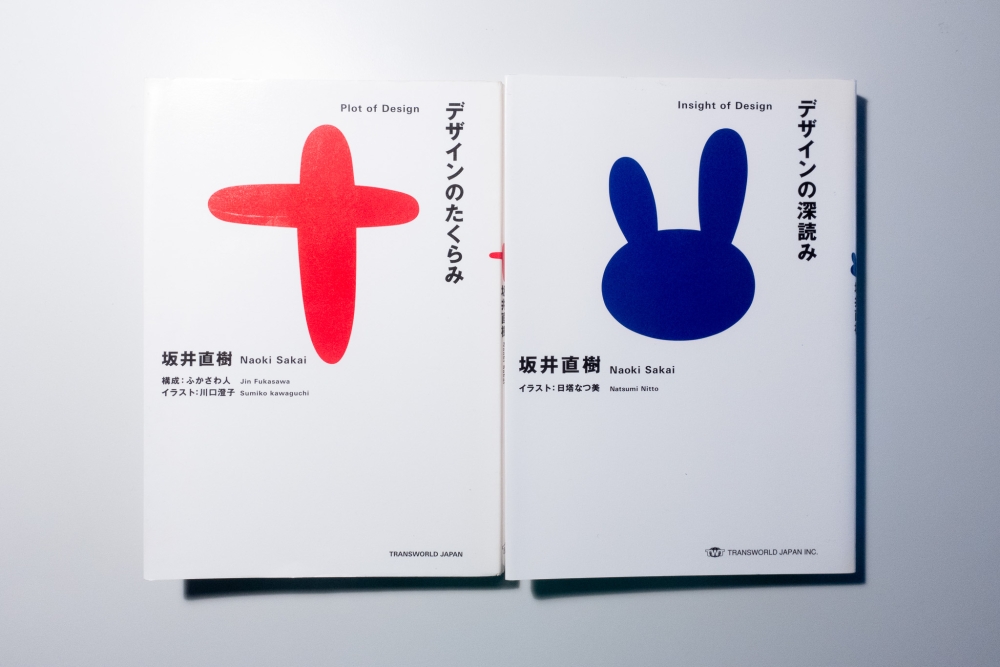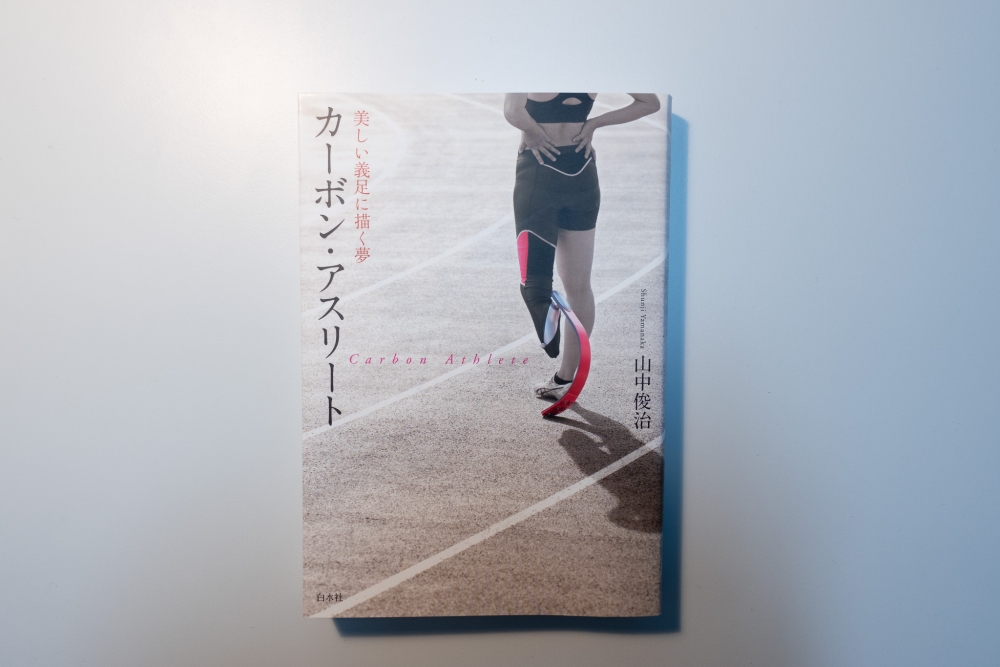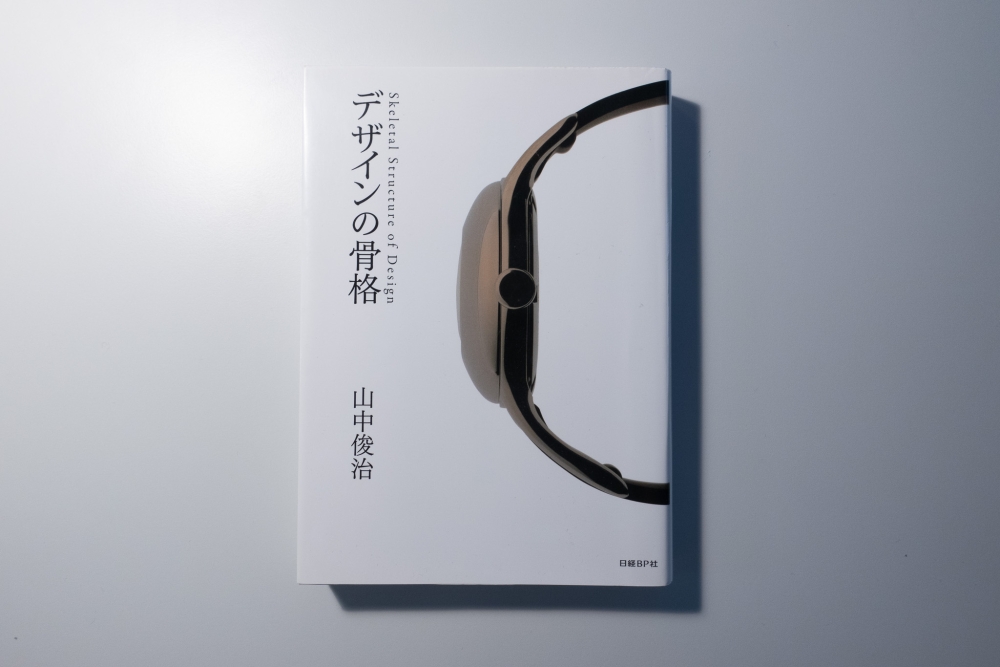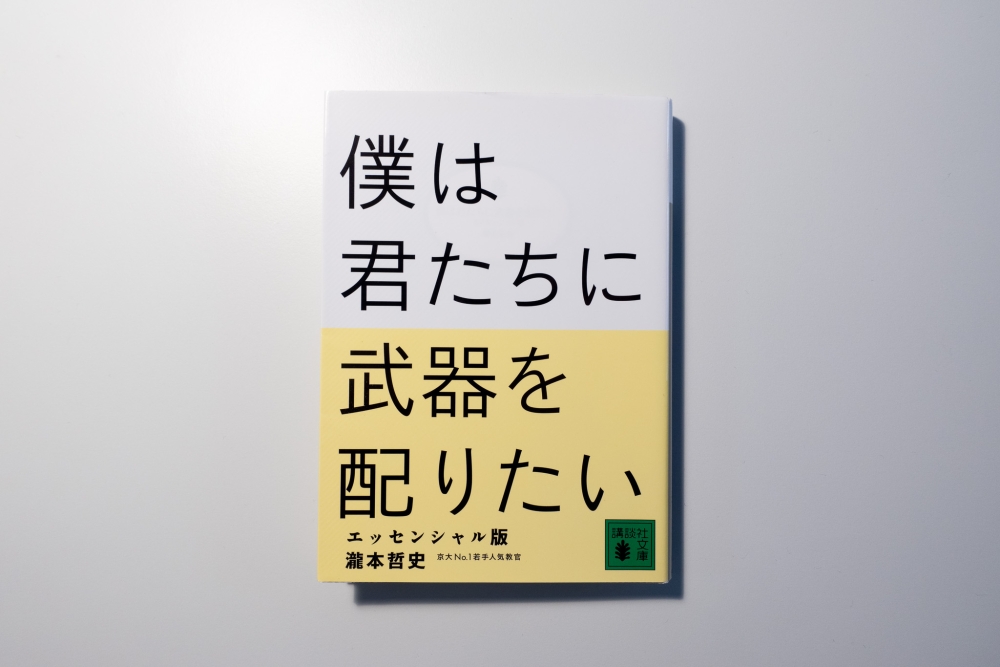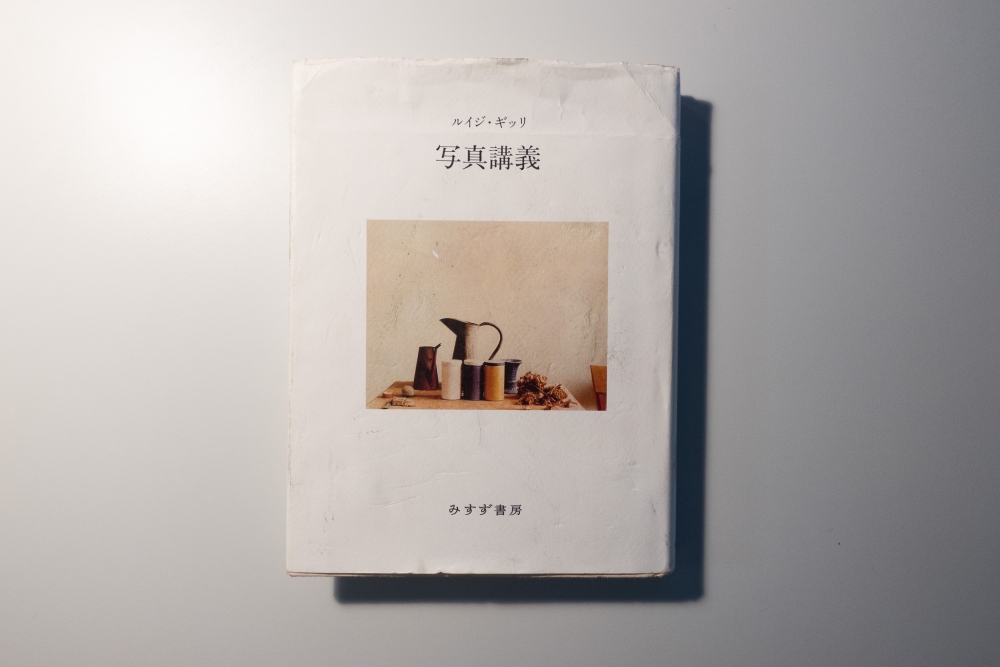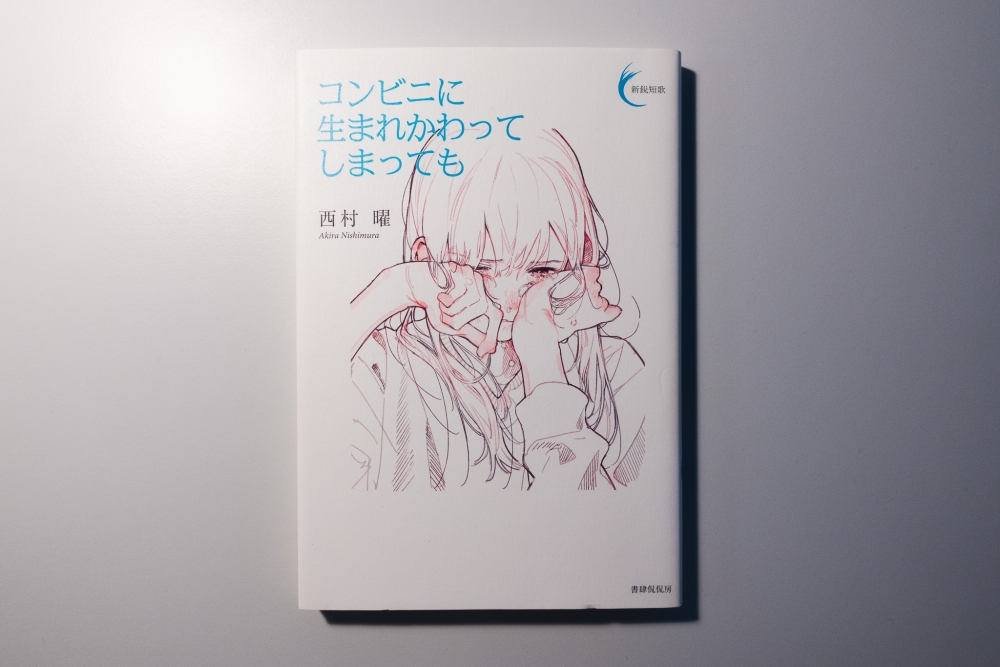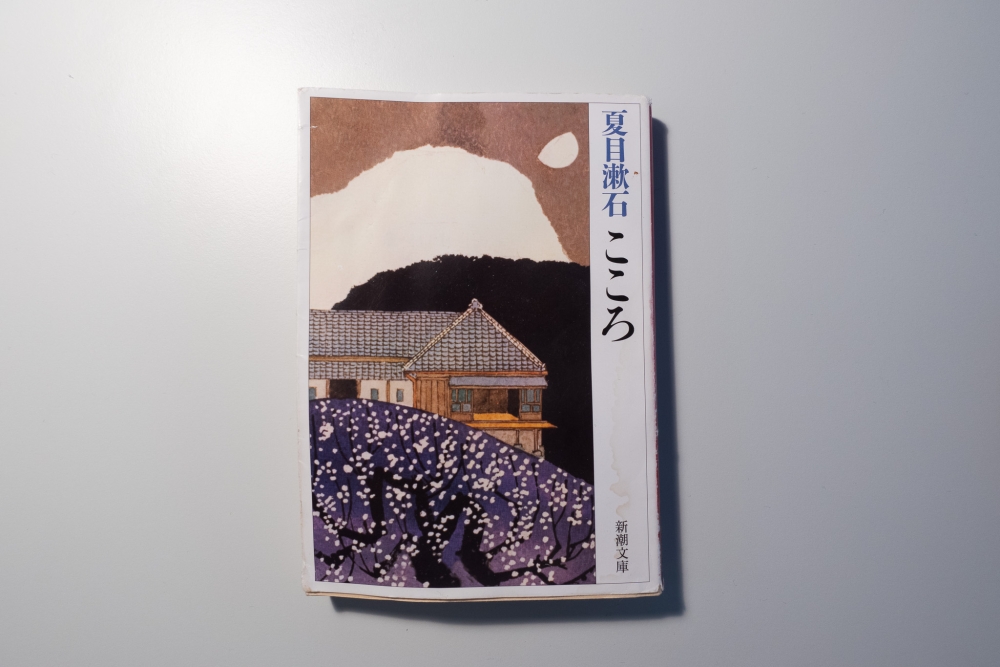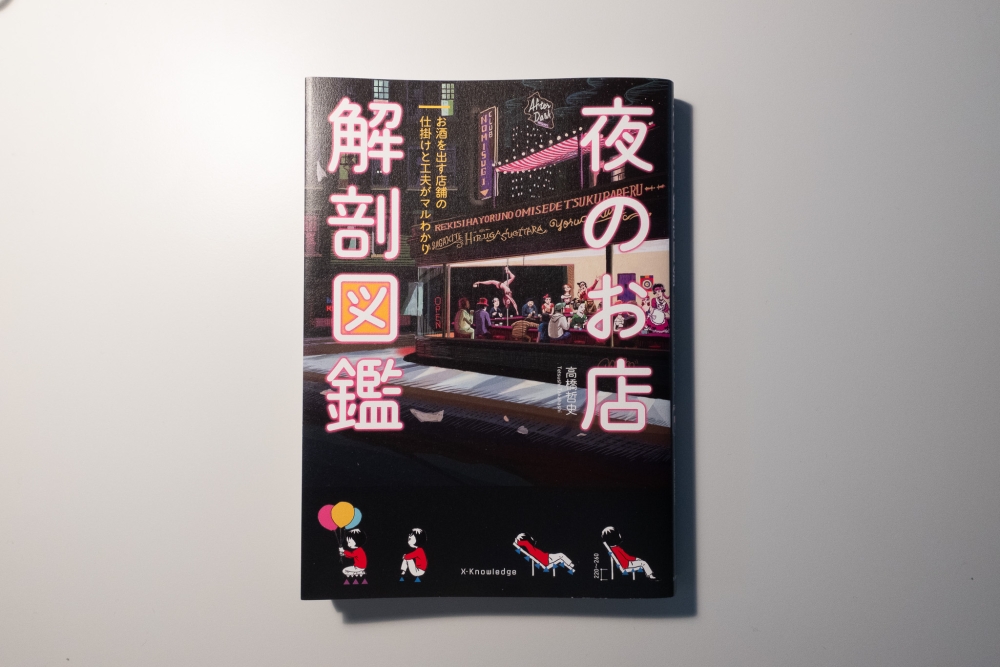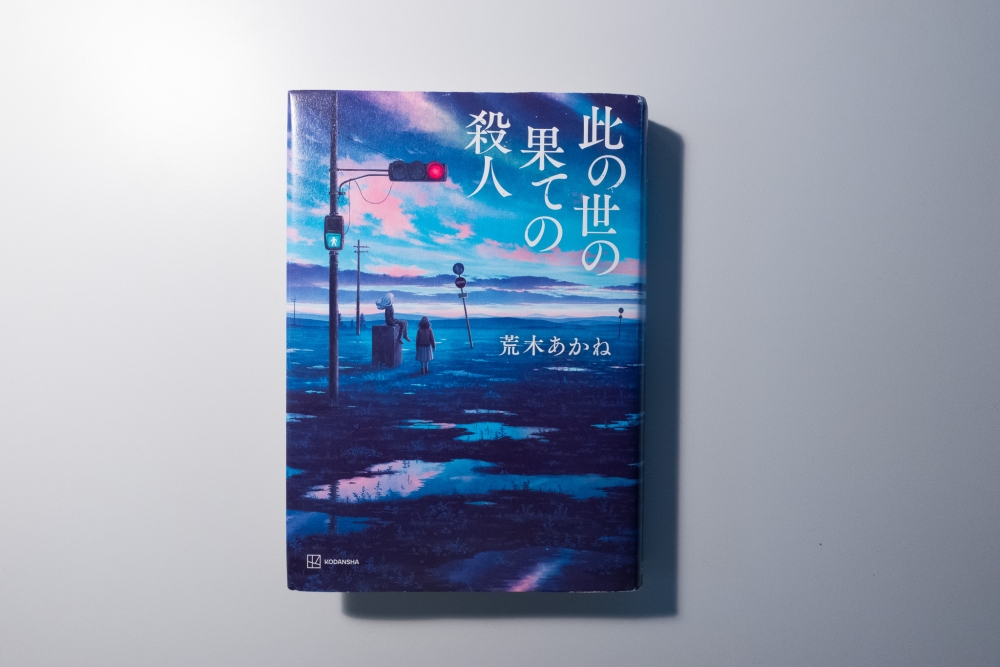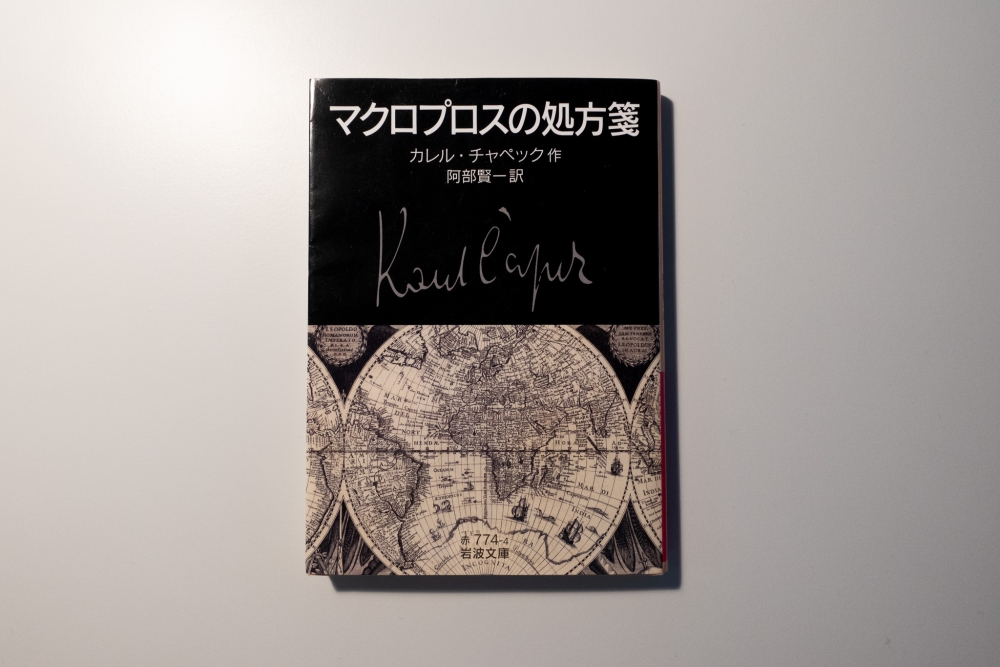Latest AllBlogs
Diary 25.07.06
2025年7月6日
Diary 25.06.15
2025年6月15日
N o.6-再会-(著:あさのあつこ)を読んだって話。
2025年6月15日
EXPO 2025 大阪・関西万博に行ってきた話
2025年6月15日
Diary 25.05.08
2025年5月8日
Diary 25.05.06
2025年5月6日
Diary 25.05.05
2025年5月5日
Diary 25.05.04
2025年5月4日
翻訳者の全技術(著:山形浩生)を読んだって話。
2025年3月14日
SHOE DOGを久しぶりに読んだって話。
2025年1月17日
Diary 2024.11.17
2024年11月17日
Diary 24.08.29
2024年8月29日
Diary 24.06.25
2024年6月25日
未来のかけら-科学とデザインの実験室-を観てきたって話。
2024年6月24日
デ・キリコ展を観てきたって話。
2024年6月24日
Diary 2024.05.16
2024年5月16日
ATTENTION SPAN-デジタル時代の「集中力」の科学-を読んだって話。
2024年5月14日
ユニクロ(著:杉本貴司)を読んだって話。
2024年5月14日
ADAPTATION – KYNEを観てきたって話。
2024年5月6日
Latest Notes
N o.6-再会-(著:あさのあつこ)を読んだって話。
2025年6月15日
翻訳者の全技術(著:山形浩生)を読んだって話。
2025年3月14日
SHOE DOGを久しぶりに読んだって話。
2025年1月17日
ATTENTION SPAN-デジタル時代の「集中力」の科学-を読んだって話。
2024年5月14日
ユニクロ(著:杉本貴司)を読んだって話。
2024年5月14日
Diary 2024.04.30
2024年4月30日
デザインのたくらみ・デザインの深読み(著:坂井直樹)を読んだって話。
2024年3月18日
カーボン・アスリート-美しい義足に描く夢-(著:山中俊治)を読んだって話。
2024年3月14日
デザインの骨格(著:山中俊治)を読んだって話。
2024年3月11日
僕は君たちに武器を配りたい(著:瀧本哲史)を読んだって話。
2024年3月8日
写真講義(著:ルイジ・ギッリ)を読んだって話。
2024年3月8日
コンビニに生まれかわってしまっても(著:西村 曜)を読んだって話。
2024年3月4日
こころ(著:夏目漱石)を読んだって話。
2024年3月4日
夜のお店解剖図鑑(著:高橋哲史)を読んだって話。
2024年3月4日
此の世の果ての殺人(著:荒木あかね)を読んだって話。
2024年3月4日
マクロプロスの処方箋(著:カレル・チャペック)を読んだって話。
2024年3月4日
街とその不確かな壁(著:村上春樹)を読んだって話。
2024年1月23日
写真前夜(著:瀧本幹也)を読んだって話。
2024年1月23日
「アメリカの制裁外交(著:杉田弘毅)を読んだって話。
2024年1月23日
Latest BookDiarys
N o.6-再会-(著:あさのあつこ)を読んだって話。
2025年6月15日
翻訳者の全技術(著:山形浩生)を読んだって話。
2025年3月14日
SHOE DOGを久しぶりに読んだって話。
2025年1月17日
ATTENTION SPAN-デジタル時代の「集中力」の科学-を読んだって話。
2024年5月14日
ユニクロ(著:杉本貴司)を読んだって話。
2024年5月14日
Diary 2024.04.30
2024年4月30日
デザインのたくらみ・デザインの深読み(著:坂井直樹)を読んだって話。
2024年3月18日
カーボン・アスリート-美しい義足に描く夢-(著:山中俊治)を読んだって話。
2024年3月14日
デザインの骨格(著:山中俊治)を読んだって話。
2024年3月11日
僕は君たちに武器を配りたい(著:瀧本哲史)を読んだって話。
2024年3月8日
写真講義(著:ルイジ・ギッリ)を読んだって話。
2024年3月8日
コンビニに生まれかわってしまっても(著:西村 曜)を読んだって話。
2024年3月4日
こころ(著:夏目漱石)を読んだって話。
2024年3月4日
夜のお店解剖図鑑(著:高橋哲史)を読んだって話。
2024年3月4日
此の世の果ての殺人(著:荒木あかね)を読んだって話。
2024年3月4日
マクロプロスの処方箋(著:カレル・チャペック)を読んだって話。
2024年3月4日
街とその不確かな壁(著:村上春樹)を読んだって話。
2024年1月23日
写真前夜(著:瀧本幹也)を読んだって話。
2024年1月23日
「アメリカの制裁外交(著:杉田弘毅)を読んだって話。
2024年1月23日